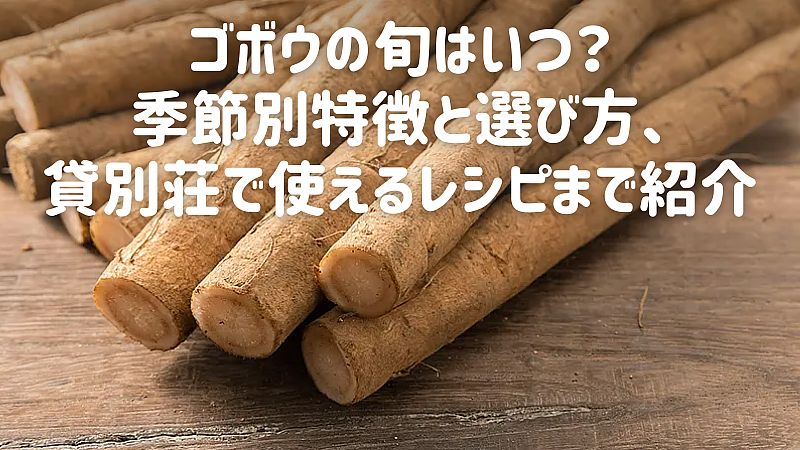ゴボウは、独特の風味とシャキシャキとした食感が特徴的な根菜です。健康にも良いことで知られており、古くから日本人に親しまれてきました。この記事では、ゴボウの旬、種類、栄養価、選び方、保存方法、そしておいしく食べるためのレシピまでを幅広く紹介していきます。
この記事では、ゴボウに関する様々な情報を網羅的に紹介しました。ぜひ、この記事を参考に、ゴボウをもっとおいしく、健康的に楽しんでください。
基本情報

ゴボウは、主に日本の関東地方や関西地方で栽培されており、年間を通して出荷されています。
主に煮物や炒め物、汁物など様々な料理に利用されています。
栄養として、食物繊維やカリウム、鉄分などが豊富に含まれています。
ゴボウの食物繊維は、腸内環境を整え、便秘を予防する効果があります。カリウムは、血圧を下げる効果があり、鉄分は貧血を予防する効果があります。
主な産地と栽培方法
ゴボウは、日本各地で栽培されていますが、特に茨城県、千葉県、愛知県、鹿児島県が有名です。関東地方では、主に秋冬に収穫される秋冬種が栽培されており、夏に収穫される夏秋種は、温暖な気候の鹿児島県や愛知県の西三河地方で栽培されています。
栽培方法は、種を直接畑にまいて育てる「直播栽培」と、一度苗床で育ててから畑に植え替える「移植栽培」の2種類があります。直播栽培は、種まきから収穫まで約5~6ヶ月かかるのに対し、移植栽培は、種まきから収穫まで約4ヶ月程度で済みます。また、移植栽培の方が、生育が揃いやすく、収量も多くなる傾向があります。
ゴボウの旬と種類

ゴボウは一年を通して楽しめる野菜ですが、旬は大きく分けて3種類あります。
・春の旬を迎える若ゴボウ: この時期のゴボウは、皮が薄く柔らかく、アクが少ないのが特徴です。土の香りが強く、みずみずしい味わいが楽しめます。
・春ごぼう・夏ごぼうとも呼ばれる「新ごぼう」: 5月頃から収穫されるゴボウで、若ゴボウよりも身が太く、アクも強くなります。しかし、栄養価が高く、香りも強いのが特徴です。
・冬の旬を楽しむスーパーで人気のゴボウ: 10月頃から収穫されるゴボウで、身が締まり、甘みが増します。アクが少なく、煮物や汁物などに向いています。
それぞれ特徴が異なるため、料理に合わせて使い分けることができます。
春の旬を迎える若ゴボウの特徴
春の若ゴボウは、みずみずしく柔らかな食感が特徴です。アクが少なく、生に近い状態で味わうことができるのも魅力の一つです。
春の若ゴボウの特徴
・味:アクが少なく、甘くみずみずしい。
・食感:柔らかく、生でも食べられる。
・大きさ:細く、短いものが多い。
・皮:薄く、皮ごと食べられる。
・旬の時期:3月下旬~5月頃
春の若ゴボウのメリット
栄養価が高い: 春の若ゴボウは、冬ゴボウに比べて水分が多く、カリウムやビタミンB群などが豊富に含まれています。
アクが少ない: アクが少ないため、下処理が簡単です。
様々な料理に使える: サラダや汁物など、様々な料理に使うことができます。
若ゴボウの選び方
・皮にハリとつやがあるもの
・ひげ根が少ないもの
・太さが均一なもの
春の若ゴボウは、アクがなく、柔らかな食感が特徴です。ぜひ、様々な料理に活用してみてください。
春ごぼう・夏ごぼうとも呼ばれる「新ごぼう」
新ごぼうは、春から夏にかけて収穫される若ごぼうのことです。皮が薄く、柔らかく、アクが少なく、甘みがあるのが特徴です。通常のゴボウよりも水分の含有量が多く、みずみずしい食感を楽しむことができます。
新ごぼうは、主に以下の特徴があります。
・皮が薄くて柔らかい:皮をむかなくてもそのまま調理できるため、栄養価を逃さず、調理の手間も省けます。
・アクが少なく、甘みがある:アクが少ないため、下ゆでなしでそのまま料理に使用できます。また、甘みがあるため、素材の味をいかした料理に最適です。
・みずみずしい食感:水分の含有量が多いことから、シャキシャキとした食感を楽しむことができます。
・栄養価が高い:新ごぼうは、通常のゴボウと同様に、食物繊維やカリウム、鉄分などの栄養素が豊富に含まれています。
新ごぼうは、さまざまな料理に利用できます。
きんぴらごぼう、サラダ、煮物、天ぷらなど、通常のゴボウと同じように使用することができます。また、皮が薄いため、炒め物やスープなどにも適しています。
新ごぼうは、4月頃から出回り始め、6月頃が最盛期となります。旬の時期に収穫された新ごぼうは、特に味が良く、栄養価も高いため、ぜひ一度味わってみてください。
冬の旬を楽しむスーパーで人気のゴボウ
冬ゴボウは、春ゴボウよりも太くて短く、アクが強いのが特徴です。
アクが強い分、栄養価も高く、冬にぴったりの食材です。
特徴として、食物繊維が豊富で、腸内環境を整える効果があります。
また、カリウムやカルシウムなどのミネラルも豊富で、高血圧や骨粗鬆症の予防にも効果があります。
<栄養素>
・カリウム:高血圧の予防
・カルシウム:骨粗鬆症の予防
・ポリフェノール:抗酸化作用
ゴボウを選ぶときは、太くて短く、ひげ根が少ないもの、皮に傷がないものを選びましょう。ゴボウの保存方法は、新聞紙に包んで冷暗所で保存するか、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。
ゴボウに含まれる栄養素と効果

ごぼうは栄養価の高い野菜です。食物繊維、ミネラル、ポリフェノールなど、体に良いとされる栄養素を豊富に含んでいます。
食物繊維:
・ごぼうに含まれる食物繊維は、便通を促進したり、コレステロール値を下げる効果があると言われています。
ミネラル:
・カリウムやカルシウム、マグネシウムなど、さまざまなミネラルが含まれています。
・カリウムは体内の塩分を排出する働きがあり、高血圧の予防に効果的です。
・カルシウムは骨の形成に不可欠なミネラルです。
・マグネシウムは筋肉の収縮やリラックスを調整する働きがあり、疲労回復効果が期待できます。
ポリフェノール:
・ごぼうには、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が多く含まれています。
・クロロゲン酸は抗酸化作用があり、活性酸素による細胞のダメージを防ぐ働きがあります。
このように、ごぼうは体に良いとされる栄養素を豊富に含んでいます。
健康維持のために、積極的にごぼうを食べるようにしましょう。
ゴボウの健康効果を支える食物繊維
ゴボウは、きんぴらごぼうや煮物など、さまざまな料理に欠かせない食材です。そのおいしさだけでなく、健康効果も注目されています。その理由のひとつが、豊富に含まれる食物繊維です。
食物繊維は、人間が消化できない植物性の繊維のことです。腸内環境を整え、便秘を予防する効果があることで知られています。また、血糖値の上昇を抑えたり、コレステロール値を下げたりする効果も期待できます。
ゴボウに含まれる食物繊維は、水溶性と不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は、水に溶けてゲル状になり、腸内環境を整える働きがあります。一方、不溶性食物繊維は、水に溶けず、腸内を掃除する働きがあります。ゴボウは、この2種類の食物繊維をバランスよく含んでいるため、腸内環境を整える効果がより高いと言われています。
1日の食物繊維の摂取量は、成人男性で20g、成人女性で18gが推奨されています。ゴボウは約100gで6gの食物繊維を含んでいるため、1日に100gほど食べれば、1日の推奨量の約30%を摂取することができます。
このように、ゴボウは食物繊維が豊富に含まれているため、健康効果が期待できます。
ゴボウに豊富に含まれるミネラルの効果
ゴボウに豊富に含まれるミネラルは、健康に様々なメリットをもたらします。
・カリウムは体内の余分なナトリウムを排出するのに役立ち、血圧を下げる効果が期待できます。
・カルシウムは骨や歯の形成に不可欠なミネラルです。
・マグネシウムは300種類以上の酵素の働きを助けるミネラルで、筋肉の収縮や神経の伝達に関与しています。
・リンは骨や歯の形成だけでなく、エネルギー代謝にも重要な役割を果たします。
・鉄は赤血球の生成に必要不可欠なミネラルです。
これらのミネラルは、それぞれが重要な働きをしていて、ゴボウを食べることで健康維持に役立てることができます。
ポリフェノールがもたらすゴボウの抗酸化作用
ゴボウに含まれるポリフェノールは、クロロゲン酸やイヌリンなどの成分です。クロロゲン酸は抗酸化作用に加え、血糖値の上昇を抑えたり、血圧を下げたりする効果も期待されています。イヌリンは水溶性食物繊維の一種で、腸内環境を整え、便秘解消や免疫力アップに効果的です。
ゴボウのポリフェノールは、抗酸化作用をはじめ、さまざまな健康効果をもたらします。日々の食生活に取り入れることで、健康維持に役立てましょう。
ごぼうの栄養をムダなく摂るコツ

ごぼうの栄養をムダなく摂るコツをご紹介します。
・皮を剥きすぎない:ごぼうの皮には、食物繊維やポリフェノールなどの栄養素が豊富に含まれています。皮を剥きすぎると、これらの栄養素を損なってしまうため、できるだけ皮を薄く剥くか、皮付きのまま調理しましょう。
・水にさらしすぎない:ごぼうを水にさらすことでアクが抜けますが、同時に水溶性の栄養素も流れ出てしまいます。水にさらす時間は短めにし、アク抜き後はすぐに調理しましょう。
これらのコツを参考に、ごぼうのおいしさと栄養を存分に味わってみてください。
皮を剥きすぎない
ゴボウの皮には、食物繊維やカリウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。 これらの栄養素は、腸内環境を整えたり、血圧を下げたり、骨を丈夫にするなどの効果があります。
特に注目したいのが、ゴボウの皮に多く含まれる「クロロゲン酸」というポリフェノールです。 クロロゲン酸は抗酸化作用があり、生活習慣病の予防にも効果があるとされています。
ゴボウの皮を剥きすぎると、これらの栄養素が一緒に剥がれてしまいます。 実際に、皮を剥いたゴボウと皮を剥いていないゴボウの栄養価を比較した研究によると、皮を剥いたゴボウは食物繊維が約30%、カリウムが約20%、マグネシウムが約15%減少することがわかっています。
ゴボウの皮は、包丁で薄く剥くか、たわしでこすって落とします。 ただし、皮を剥きすぎると栄養が減ってしまうので、できるだけ薄く剥くようにしましょう。 また、黒ずんでいる部分や傷んでいる部分は取り除いてください。
水にさらしすぎない
ゴボウは、食物繊維やミネラルが豊富に含まれる健康野菜です。しかし、調理の際に水にさらしすぎると、せっかくの栄養素が流れ出てしまう恐れがあります。
ゴボウに含まれる水溶性食物繊維は、水にさらすことで溶け出してしまいます。水溶性食物繊維は、腸内環境を整え、コレステロール値を下げるなどの効果があるため、できるだけ体内に取り込みたい栄養素です。また、ゴボウの香りや風味も水に溶け出すため、水にさらしすぎると、ゴボウ本来の美味しさが損なわれてしまいます。
ゴボウの水にさらしすぎを防ぐには、以下の点に注意しましょう。
・水にさらす時間はできるだけ短くする:アクが気になる場合は、さっと水洗いする程度にとどめましょう。
・酢水ではなく、水にさらす:酢水にさらすと、ゴボウの灰汁が抜けるのは早くなりますが、同時に水溶性食物繊維も流れ出てしまいます。
・カットした後はすぐに水にさらさない:カットしたゴボウは空気に触れると変色するため、すぐに水にさらしたくなりますが、変色を防ぐには、酢水ではなく、水にさらすのがおすすめです。
ゴボウは栄養価の高い野菜ですが、水にさらしすぎるとせっかくの栄養素が流れ出てしまいます。
水にさらす時間はできるだけ短くし、酢水ではなく水にさらすようにしましょう。
また、カットした後はすぐに水にさらさず、変色を防ぐために水にさらすようにしましょう。
おいしいゴボウを選ぶポイント

ゴボウは、独特の風味と歯ごたえが魅力的な食材です。おいしく調理するためには、新鮮で良質なゴボウを選ぶことが大切です。ここでは、おいしいゴボウを選ぶポイントをご紹介します。
<ポイント>
・土付きのゴボウを選ぶ:土付きのゴボウは、鮮度が保たれやすく、水分を多く含んでいます。
・適切な太さのゴボウを選ぶ:1.5cm~2.5cmほどの太さのゴボウが、アクが少なく、やわらかく食べやすいです。
・ヒゲ根の少ないゴボウを選ぶ:ヒゲ根の多いゴボウは、アクが強く、硬いので避けたほうが良いでしょう。
これらのポイントを押さえて、おいしいゴボウを選びましょう。次の章では、ゴボウの選び方についてさらに詳しく解説します。
土付きのゴボウを選ぶ理由
冬は寒さに当たって甘みが増し、アクが少なく、やわらかいゴボウが旬を迎えます。ゴボウを選ぶときは、鮮度が落ちにくく、水分を多く含んでいるため、みずみずしく、やわらかい土付きのものがおすすめです。
土付きのゴボウは、皮がむきやすく、アクが抜けやすいというメリットもあります。保存も簡単で、新聞紙に包んで、風通しの良い冷暗所で保存すれば、1週間程度日持ちします。
適切な太さのゴボウを選び方
ゴボウの太さは、若ゴボウ、中ゴボウ、大ゴボウの3種類に分けられます。それぞれの特徴は以下の通りです。
・若ゴボウ:1.5cm以下
・中ゴボウ:1.5cm~3cm
・大ゴボウ:3cm以上
料理によって適切な太さを選ぶことが大切です。きんぴらごぼうやゴボウサラダなど、柔らかく仕上げたい料理には若ゴボウや中ゴボウが適しています。一方、ゴボウ茶やゴボウチップスなど、アクの強さを活かしたい料理には大ゴボウが適しています。
また、ゴボウの太さはアクの強さだけでなく、食感にも影響します。若ゴボウは柔らかく、中ゴボウは歯ごたえがあり、大ゴボウは硬いという特徴があります。
ゴボウを選ぶ際には、料理に合わせて太さを選ぶようにしましょう。
ヒゲ根の少ないゴボウを選ぶコツ
ゴボウは、一年を通して手に入る野菜ですが、旬は春と冬です。春に収穫される若ゴボウは柔らかく、アクが少ないのが特徴です。冬に収穫されるゴボウは、皮が固く、アクが強いですが、長期保存に向いています。
<ヒゲ根の少ないゴボウを選ぶコツ>
ヒゲ根が少ないゴボウは、皮むきが楽になるだけでなく、食感が良くなります。ヒゲ根が少ないゴボウを選ぶコツをいくつかご紹介します。
1:表面が滑らかでツヤのあるもの
表面がザラザラしているものは、ヒゲ根が多く、皮むきが大変になります。
2:太さが均一なもの
太さが均一でないものは、ヒゲ根が密集している部分があるため、皮むきが難しくなります。
3:切り口が白いもの
切り口が黒ずんでいるものは、鮮度が落ちている可能性があります。鮮度の良いゴボウは、切り口が白く、水分が多いです。
4:軽いもの
同じ大きさでも、軽いものはヒゲ根が少ない傾向にあります。
これらのポイントを参考に、ヒゲ根が少ないゴボウを選びましょう。
ゴボウの保存方法と保存期間

ゴボウは鮮度が落ちやすい野菜ですが、正しい方法で保存すれば長くおいしく食べることができます。ここでは、土付きゴボウと洗いゴボウのそれぞれに適した保存方法と期間をご紹介します。
土付きゴボウの保存方法と期間
以下の方法での保存が適切です。
・新聞紙に包んで、冷暗所で保存します。
・保存期間は2週間程度です。
保存期間をさらに延ばしたい場合は、土付きゴボウを新聞紙で包んだ後、段ボール箱に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存すると、2週間程度日持ちします。
土付きゴボウを調理する際は、土をきれいに洗い落としてから、皮をむいて使用してください。
洗いゴボウの保存方法と期間
以下の方法での保存が適切です。
・水洗いして、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。
・ポリ袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存します。
・保存期間は1週間程度です。
土付きゴボウの方が保存期間が長いですが、洗いゴボウはそのまま調理できるので便利です。どちらの保存方法を選ぶかは、ご自身の状況に合わせて判断してください。
貸別荘やコテージで使えるゴボウを使ったレシピ
貸別荘やコテージで調理する際には、手軽に作れて美味しいメニューが重宝します。そんな時にオススメなのが、ゴボウを使ったレシピです。
ゴボウは日持ちが良く、アウトドアでも保存がしやすい食材です。また、きんぴらゴボウやゴボウとツナのサラダ、ゴボウチップスなど、様々なバリエーションを楽しむことができます。
きんぴらごぼう

きんぴらは、ゴボウが主役の、歯応えが楽しい常備菜。様々な野菜を一緒に炒めても美味しくいただけます。
<材料>
・ゴボウ:1本
・人参:1/2本
・唐辛子:1本
・ごま油:大さじ1
・醤油:大さじ2
・砂糖:大さじ1
・酒:大さじ1
・みりん:大さじ1
・白ごま:適量
<作り方>
1:ゴボウは皮をこそげ取り、ささがきにして水にさらす。人参もささがきにする。
2:唐辛子は種を取り除き、小口切りにする。
3:フライパンにごま油を熱し、ゴボウと人参を炒める。しんなりしてきたら唐辛子を加えてさらに炒める。
4:調味料を全て加えて水分がなくなるまで炒める。
5:器に盛り付け、白ごまを振る。
きんぴらゴボウは、日持ちもするので、作り置きにも最適です。お弁当のおかずにもぴったりです。
ごぼうとツナのサラダ

ゴボウは、食物繊維、ミネラル、抗酸化物質が豊富な万能野菜です。また、低カロリーでヘルシーなため、サラダにもぴったりです。
このレシピでは、ゴボウとツナを組み合わせた、簡単で美味しいサラダを紹介します。
<材料>
・ごぼう:1本(約150g)
・ツナ缶(水煮またはオイル漬け):1缶(70~80g)
・にんじん:1/3本
・マヨネーズ:大さじ2~3
・醤油:小さじ1
・酢:小さじ1
・塩:少々
・こしょう:少々
・白ごま:お好みで
<作り方>
1:ごぼうをよく洗い、皮を包丁の背で軽くこそげ取ります。
2:細切りにしたら、水に5分ほどさらしてアクを抜きます。
3:にんじんも細切りにします。
4:鍋に湯を沸かし、塩少々を加えます。ごぼうとにんじんを2~3分茹で、ザルにあげて冷ましておきます。
5:ツナ缶の汁気を切っておきます。オイル漬けの場合は軽く油を切る程度でOK。
6:ボウルに茹でたごぼうとにんじん、ツナを入れます。
7:マヨネーズ、醤油、酢、塩、こしょうを加え、全体をよく混ぜます。
8:白ごまをふりかけて完成!
1:ごぼうをよく洗い、皮を包丁の背で軽くこそげ取ります。
2:細切りにしたら、水に5分ほどさらしてアクを抜きます。
3:にんじんも細切りにします。
4:鍋に湯を沸かし、塩少々を加えます。ごぼうとにんじんを2~3分茹で、ザルにあげて冷ましておきます。
5:ツナ缶の汁気を切っておきます。オイル漬けの場合は軽く油を切る程度でOK。
6:ボウルに茹でたごぼうとにんじん、ツナを入れます。
7:マヨネーズ、醤油、酢、塩、こしょうを加え、全体をよく混ぜます。
8:白ごまをふりかけて完成!
<栄養価>
このサラダは、食物繊維、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富です。
また、低カロリーでヘルシーなため、ダイエット中の方にもおすすめです。
ごぼうチップス

貸別荘やコテージで簡単に作れる、ゴボウチップスのレシピです。パリパリの食感とゴボウの香ばしさが楽しめる一品です。
<材料>
・ゴボウ 1本
・オリーブオイル 大さじ1
・塩 少々
<作り方>
1:ゴボウは皮をこそげ落とし、薄切りにします。
2:ボウルにゴボウとオリーブオイルを入れて混ぜ合わせます。
3:クッキングシートを敷いた天板にゴボウを広げます。
4:180度に予熱したオーブンで15〜20分、こんがりと焼き色がつくまで焼きます。
5:焼き上がったら、塩を振って完成です。
<ポイント>
・ゴボウは薄切りにすることで、パリパリの食感に仕上がります。
・オリーブオイルは、ゴボウにまんべんなく絡ませるようにしましょう。
・焼き時間は、ゴボウの太さやオーブンによって調整してください。
<アレンジ>
・仕上げにブラックペッパーやガーリックパウダーを振ってもおいしいです。
・カレー粉やクミンパウダーなどを加えると、エスニックな風味になります。
まとめ

ごぼうは、食物繊維が豊富で独特の風味と食感を持つ魅力的な食材です。今回ご紹介した3選は、貸別荘やコテージで手軽に作れるものばかりなので、ぜひ試してみてください。ごぼうの新しい魅力を発見できるはずです。
揚げ物、煮物、ご飯もの、サラダ、汁物、パスタなど、ごぼうは様々な料理に姿を変え、食卓を豊かにしてくれます。家族や仲間と、美味しいごぼう料理を囲んで、素敵な時間を過ごしてください。