そら豆は春から初夏にかけて旬を迎える豆です。栄養価が高く、タンパク質、ビタミンC、ビタミンB群、葉酸、食物繊維、カリウムなどを豊富に含んでいます。
新鮮なそら豆は、さやが緑色でふっくらとしていて、実が詰まっているものを選びましょう。
そら豆の旬な時期

旬の時期は、地域によって若干異なりますが、一般的には5月上旬から7月上旬までです。特に5月下旬から6月中旬にかけてが最盛期となります。
春から初夏にかけて、暖かくなってきた時期に収穫されるそら豆は、鮮やかな緑色をしていて、みずみずしく、甘みがあります。旬の時期にはスーパーや八百屋さんで新鮮なそら豆を見つけることができます。
そら豆は、そのまま食べても美味しいですが、料理にも幅広く使うことができます。シンプルに塩ゆでして食べるのもよし、そら豆ごはんや焼きそら豆など、さまざまな料理に活用できます。また、栄養価も高く、タンパク質やビタミンC、食物繊維などが豊富に含まれています。
そら豆の栄養

そら豆は、タンパク質、ビタミンC、ビタミンB群、葉酸、食物繊維、カリウムなど、豊富な栄養素を含んでいます。
・タンパク質:植物性タンパク質の優れた供給源です。100gのそら豆には、約7gのタンパク質が含まれています。
・ビタミンC:抗酸化作用を持つビタミンCが豊富です。100gのそら豆には、約25mgのビタミンCが含まれています。
・ビタミンB群:エネルギー代謝に重要なビタミンB群、特にビタミンB1、B2、B6が豊富です。
・葉酸:胎児の健康に重要な葉酸が豊富です。100gのそら豆には、約160μgの葉酸が含まれています。
・食物繊維:消化を促進する食物繊維が豊富です。100gのそら豆には、約8gの食物繊維が含まれています。
・カリウム:血圧を下げる効果のあるカリウムが豊富です。100gのそら豆には、約400mgのカリウムが含まれています。
タンパク質
そら豆は、私たちの健康を維持するために必要なさまざまな栄養素が豊富に含まれています。その中でも、タンパク質はそら豆の重要な栄養素の一つです。
タンパク質は、筋肉や臓器、皮膚などの身体の組織を作るために不可欠な栄養素です。また、酵素やホルモンなどの重要な物質を作る役割も果たしています。そら豆には、100gあたり5.4gのタンパク質が含まれており、これは他の豆類と比較しても多い量です。
タンパク質は、私たちの健康を維持するために毎日摂取する必要があります。成人男性の場合、1日に約60g、成人女性の場合は約50gのタンパク質を摂取することが推奨されています。そら豆は、この推奨量を満たすために役立つ食品です。
そら豆のタンパク質は、植物性タンパク質です。植物性タンパク質は、動物性タンパク質と比較して、コレステロールや飽和脂肪酸が少ないという特徴があります。そのため、健康的な食生活を送るために、動物性タンパク質よりも植物性タンパク質を多く摂取することが推奨されています。
ビタミンC
そら豆は、ビタミンCを豊富に含んでいます。ビタミンCは、抗酸化作用があり、免疫力を高める働きがあります。また、コラーゲンの生成を促進するため、肌の弾力性を維持するのにも役立ちます。
そら豆に含まれるビタミンCの量は、100gあたり25mgで、これは1日の推奨摂取量の約30%に相当します。
そら豆のビタミンCは、水溶性であるため、加熱調理によって損失しやすいです。そのため、そら豆はできるだけ生で食べるか、さっと茹でる程度にとどめておくとよいでしょう。
ビタミンB群
そら豆に含まれるビタミンB群には、様々な種類があります。
・ビタミンB1 (チアミン):エネルギー代謝を促進し、疲労回復に効果的です。
・ビタミンB2 (リボフラビン):皮膚や粘膜の健康維持に役立ちます。
・ビタミンB6 (ピリドキシン):タンパク質の代謝を助け、免疫力を高める効果があります。
・ビタミンB12 (コバラミン):赤血球の形成を促進し、貧血予防に効果的です。
これらのビタミンB群は、一緒に働くことで、エネルギー代謝を促進し、疲労回復、免疫力向上、貧血予防などの効果を発揮します。 また、精神を安定させたり、肌荒れを防いだりする効果も期待できます。
葉酸
そら豆の葉酸は、ビタミンB群の一種で、細胞分裂やDNAの合成に関与しており、胎児の成長や発育に欠かせない栄養素です。また、貧血予防や動脈硬化の予防にも効果があるとされています。
そら豆には、100gあたりに約240μgの葉酸が含まれています。これは、成人が1日に必要な葉酸量の約60%に相当します。葉酸は水溶性ビタミンなので、茹でたり、蒸したり、炒めたりしても、栄養素が流れ出てしまう心配はありません。
食物繊維
そら豆は、食物繊維が豊富な野菜です。 食物繊維は、腸内環境を整え、便秘を防ぐ効果があります。 また、コレステロール値を下げたり、血糖値の上昇を抑えたりする効果も期待できます。 100gあたりの食物繊維含有量は、5.1gと、野菜の中でもトップクラスです。
食物繊維は、水溶性と不溶性の2種類に分けられます。 そら豆に含まれる食物繊維は、不溶性食物繊維がほとんどです。 不溶性食物繊維は、水分を吸収して膨張し、便のかさを増やすことで、腸の蠕動運動を活発にします。
カリウム
そら豆は、カリウムが豊富に含まれているため、健康維持に役立つ食品です。カリウムは、血圧の正常化や筋肉の収縮、神経伝達をサポートする働きがあります。カリウム不足は、高血圧や筋肉のけいれん、疲労などの症状を引き起こす可能性があるため、積極的に摂取することが大切です。
100gのそら豆には、約430mgのカリウムが含まれています。これは、成人が1日に必要とするカリウム量の約10%に相当します。
新鮮なそら豆の選び方

そら豆は初夏が旬の野菜で、柔らかくほくほくとした食感と甘みが特徴です。美味しいそら豆を選ぶには、いくつかのポイントがあります。
■1:さやの色と形
新鮮なそら豆は、さやが鮮やかな緑色で、ふっくらとして張りのあるものが良いでしょう。さやにシワが寄っていたり、茶色く変色しているものは鮮度が落ちています。また、さやの形が曲がっていたり、いびつなものは避けた方が良いでしょう。
■2:豆の硬さ
さやを開いて中の豆をチェックしましょう。豆はふっくらとしていて、指で押すと弾力があるものが新鮮です。豆が硬かったり、しぼんでいるものは鮮度が落ちています。
■3:豆の大きさ
豆の大きさは好みによって異なりますが、一般的には大きめの豆の方が甘みが強く、食べ応えがあります。しかし、大きすぎる豆は硬い場合があるので注意が必要です。
■4:さやの中の空洞
さやがふっくらとしていても、中の豆がスカスカになっていることがあります。豆と豆の間に隙間が空いていないものを選びましょう。
■5:産地と時期
そら豆は産地や時期によって味が異なります。国産のそら豆は5月から6月頃に旬を迎えます。北海道や東北地方のそら豆は甘みが強く、関東や関西のそら豆はコクがあります。
以上のポイントを抑えて、新鮮で美味しいそら豆を選びましょう!
そら豆の保存方法

そら豆は鮮度が落ちやすい野菜です。保存方法を誤ると、鮮度が落ちてしまい、本来の美味しさを楽しむことができなくなってしまいます。ここでは、そら豆の保存方法について、冷蔵保存と冷凍保存の2つの方法を紹介します。
冷蔵保存
そら豆を冷蔵保存する場合は、以下の手順に従ってください。
1:さやから豆を取り出す。
2:豆を水洗いして汚れを落とす。
3:水気をよく拭き取る。
4:保存袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存する。
冷蔵保存の目安は、2~3日です。
濡れたまま保存すると、傷みやすくなります。他の野菜や果物と一緒に保存すると、エチレンガスによって傷みが早まることがあります。冷蔵保存でも、時間が経つにつれて風味が落ちてきます。
冷凍保存
そら豆は冷凍保存が可能です。冷凍することで、長期間保存できるだけでなく、鮮度も保つことができます。
冷凍保存方法は以下の通りです。
1:さやから出したそら豆を塩ゆでして、薄皮をむきます。
2:粗熱が取れたら、ジッパー付きの保存袋に入れて、空気を抜いて封をします。
3:冷凍庫で保存します。
冷凍したそら豆は、自然解凍するか、凍ったまま調理に使用できます。
冷凍保存の際の注意点としては、以下のことが挙げられます。
・生のままで冷凍すると、解凍後に食感が悪くなるため、必ず塩ゆでしてから冷凍する。
・冷凍保存期間は、約1ヶ月が目安です。
・再冷凍は避ける。
そら豆の下ごしらえ

下ごしらえの方法をご紹介します。
■1:さやから豆を取り出す
さやの両端を手で持って、左右に引っ張ると簡単に開きます。中に2~3粒の豆が入っているので、取り出しましょう。
■2:豆の周りの薄皮を取る
薄皮は硬くて食べにくいので、取り除きます。爪で豆をつまんで、薄皮をむきましょう。
■3:豆の両端の黒い筋を取る
黒い筋は苦味があるので、取り除きます。爪で摘んで取り除きましょう。
■4:水洗いする
水でさっと洗い、汚れやゴミを取り除きます。
<ポイント>
・薄皮が破けてしまうと食感が悪くなるので、丁寧に剥きましょう。
・茹ですぎると豆がやわらかくなり過ぎるため、注意しましょう。
・下ごしらえをしたそら豆は、そのまま食べても、料理に使用してもOKです。
そら豆と相性の良い食材とは?

そら豆は、様々な食材と相性が良いことで知られています。
ここでは、その中でも特にオススメの食材をいくつかご紹介します。
■1:チーズ
そら豆のクリーミーな食感とチーズの濃厚さは、最高の組み合わせです。特に、パルメザンチーズやゴルゴンゾーラチーズとの相性が良く、サラダやパスタ、リゾットなどによく使われます。
■2:ベーコン
そら豆とベーコンの塩気と旨味は、お互いを引き立て合います。特に、カリカリに焼いたベーコンとそら豆を合わせたサラダは、シンプルながら絶品です。
■3:トマト
そら豆とトマトの爽やかな酸味と甘みは、夏にぴったりの組み合わせです。特に、トマトとそら豆を合わせたパスタやサラダは、さっぱりとした味わいで人気があります。
■4:アボカド
そら豆とアボカドのクリーミーな食感は、よく似ています。特に、アボカドとそら豆を合わせたサラダやディップは、濃厚な味わいとクリーミーな口当たりが楽しめます。
■5:ハーブ
そら豆とハーブの爽やかな香りは、お互いを引き立て合います。特に、バジルやディル、ミントとの相性が良く、サラダやスープ、ソースなどによく使われます。
これらの食材を組み合わせることで、そら豆の新しい魅力を発見することができます。ぜひ、様々な組み合わせを試してみてくださいね。
貸別荘やコテージで使えるそら豆を使ったレシピ

貸別荘やコテージで料理をする際、そら豆はぜひ取り入れたい食材です。シンプルに塩ゆでしてそのまま食べるだけでもおいしいですが、様々な料理にアレンジすることができます。
そら豆の塩ゆで
そら豆はシンプルに塩ゆでして食べるだけでも、その甘味とほっくりとした食感が楽しめます。
<材料>
・そら豆:200g
・塩:適量
・水:適量
<作り方>
1:そら豆の両端を切り落とす。
2:鍋にたっぷりの水を入れ、沸騰したら塩を加える。
3:そら豆を加えて3分ほど茹でる。
4:茹で上がったらザルに上げて冷ます。
5:薄皮をむいて出来上がり。
<ポイント>
・茹で時間はそら豆の大きさによって調整してください。
・薄皮をむく際に豆を傷つけないように注意してください。
・塩加減はお好みで調整してください。
そら豆の塩ゆで以外にも、そら豆ご飯や焼きそら豆など様々な料理に活用できます。ぜひ、旬のそら豆を味わってみてください。
そら豆ご飯
そら豆は、初夏を代表する野菜の一つです。ビタミンCや食物繊維が豊富で、栄養価の高い食材です。そら豆ご飯は、そら豆の旨味と甘みがご飯に染み込んで、とても美味しい一品です。
<材料>
・米:2合
・そら豆:150g
・水:360ml
・塩:小さじ1
・酒:大さじ1
・みりん:大さじ1
・醤油:大さじ1
<作り方>
1:そら豆はさやから出して、薄皮をむきます。
2:米を研いで炊飯器にセットします。
3:水、塩、酒、みりん、醤油を加えて軽く混ぜます。
4:そら豆を加えて、炊飯器のスイッチを入れます。
5:炊き上がったら、全体を混ぜ合わせて出来上がりです。
<ポイント>
・そら豆はさやから出すときに、薄皮も一緒にむいておくと、食べやすくなります。
・そら豆は冷凍保存もできます。冷凍する場合は、薄皮をむいてから冷凍してください。
・そら豆ご飯は、おにぎりにしても美味しいです。
焼きそら豆
そら豆をシンプルに焼くだけのお手軽レシピです。香ばしい香りとホクホクした食感を味わえます。
<材料>
・そら豆(サヤ付き):適量
・塩:適量
・オリーブオイル:適量
・黒こしょう:お好みで
<作り方>
1:そら豆をサヤから取り出し、薄皮をむく。
2:バーベキューグリルを中火で予熱する。
3:そら豆に塩とオリーブオイルをまぶし、グリルに並べて焼く。
4:時々転がしながら、表面に軽く焼き色がつくまで5~7分焼く。
5:火から下ろし、お好みで黒こしょうを振って出来上がり。
<ポイント>
・皮が焦げるのを防ぐために、そら豆に薄くオリーブオイルを塗ります。
・焼き上がったらすぐに皮をむくと、より一層美味しく食べられます。
・黒こしょうの他にも、ガーリックパウダーやパプリカパウダーなどお好みのスパイスをかけてアレンジもできます。
焼きそら豆はそのまま食べても美味しいですし、サラダやパスタのトッピングなどにも使えます。貸別荘やコテージでバーベキューをする際にもおすすめのレシピです。
まとめ

そら豆の旬は春から初夏にかけて。鮮やかな緑色とほくほくした食感が魅力で、旬の時期ならではの甘みを楽しめます。
栄養面では、たんぱく質や食物繊維、ビタミンB群が豊富で、美容や健康に役立つ食材です。
塩ゆでや焼きそら豆のシンプルな食べ方はもちろん、パスタやスープ、かき揚げにしても美味しくいただけます。
旬のそら豆は味も栄養価も格別なので、ぜひいろいろなレシピで楽しんでみてください。
春の味覚を堪能しながら、貸別荘・コテージでの食卓を彩りましょう。
栄養面では、たんぱく質や食物繊維、ビタミンB群が豊富で、美容や健康に役立つ食材です。
塩ゆでや焼きそら豆のシンプルな食べ方はもちろん、パスタやスープ、かき揚げにしても美味しくいただけます。
旬のそら豆は味も栄養価も格別なので、ぜひいろいろなレシピで楽しんでみてください。
春の味覚を堪能しながら、貸別荘・コテージでの食卓を彩りましょう。
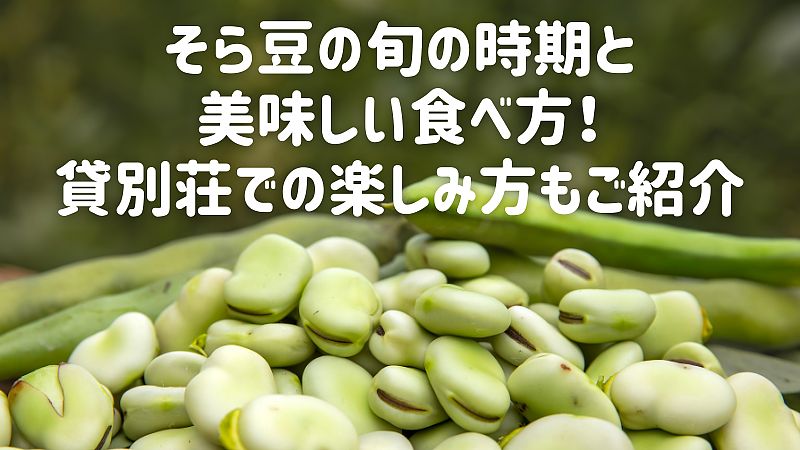.png)